連合演劇発表会鑑賞上の注意
1.会場に入ったら
会場での一般的な注意やマナーです。ご確認下さい。
◆開始時間
上演の開始時間は前後することがありますので、予定時間より早めにお越し下さい。
◆飲食
ホール内での飲食は禁止です。
◆喫煙
喫煙は喫煙所でお願いします。特に中学生の大会であることにご配慮頂き、他の場所での喫煙はお止め下さい。
◆拍手
開演時の拍手はご遠慮下さい。上演中に、演技に感動して自然に起こる拍手は制限しませんが、ストーリーの進行を妨げないように、充分ご注意下さい。
◆差し入れ
差し入れ等は、各学校のルールに従って行って下さい。ビン、カンやペットボトル禁止等、容器に制限のある場合もありますので、顧問にご確認下さい。
◆コート
厚手の服は音を吸ってしまいますので、ホール内に入ったら、コートやジャンパーの類は脱いで下さい。日本には、残念ながら、クロークが整備されていませんので、椅子の下に入れるのが、マナーとなっています。
2.上演中の注意
上演中のマナーの大原則は、「舞台と観客の集中を妨げない。」ということです。具体的に言うと、「余計な音や光を漏らさない。」ということに尽きます。よく、「フラッシュは、照明効果の妨げになるのでご遠慮下さい。」という説明がされることがあります。わかりやすいように、そう表現していますが、実際は、こちらの理由の方が重要です。
皆さん、舞台に影響を与える様なことは、しないように気を使って下さいますが、隣の席で、真剣に舞台を見ている方のことは、つい、忘れがちです。舞台に届かない音だから良いだろうとか、少しくらい構わないだろうと言う考え方は禁物です。
舞台上は夢の世界です。心ないフラッシュや携帯の音で現実に引き戻された観客は、なかなかもう一度、夢の中に入っていくことが出来ません。これは、皆さんに練習の成果を見て貰おうと頑張っている、生徒達の足を引っ張ることになります。
まして、この大会は、都大会に出場する代表を決めるコンクールも兼ねています。余計な音や光は、公平な審査の妨げにもなります。
ところが、フラッシュを焚かれる方や、ビデオのスイッチの電子音を立てられる方のほとんどが、保護者の方です。お子さんの晴れ舞台を、記録にとどめたい気持ちはよくわかりますが、ご協力下さいますようお願いします。
◆携帯
携帯電話やPHS等は、マナーモードではなく電源を切って下さい。バイブにしていても、近くの観客には音がハッキリ聞こえます。また、時計のアラームや時報等もオフにしておいて下さい。
◆カメラ
カメラのフラッシュやストロボは、大変集中を妨げますので、厳禁です。高感度のフィルム(ASA400〜800)を使用する等、工夫して下さい。また、一眼レフのシャッター音も非常に響きます。良い画を取りたいのは山々ですが、ご理解下さい。
◆ビデオ
ビデオ撮影は自由ですが、他のお客様の迷惑にならないように、なるべく最後方でお願いします。止む終えず、中央や前方の席で撮影する場合は、液晶画面は閉じて下さい。また、操作時の「ピピッ」という電子音は、メニューで消すことが出来ますので、事前にマニュアルに従って、設定をオフにしておいて下さい。
◆ポリ袋
コンビニ等のポリ袋は、少しの動作で非常に大きな音がします。なるべく、バッグ等を用意して頂いて、買ってきた昼食等の袋が、音を立てないようにお願いします。
◆パンフレット
上演中に配役等、気になることがあっても、パンフレット等をいじらないようにして下さい。紙のカサカサ言う音は、非常に耳障りです。
◆カバン
いわずもがなですが、現実には残念ながら、上演中にカバンをガサゴソ言わす方がいらっしゃいます。めがね等必要なものは、あらかじめ取り出しておいて下さい。
◆お子さん
小さなお子さんが、泣いたり、騒いだりするのは仕方のないことですし、各家庭のご事情で、会場に連れてこないと観劇が出来ない場合もあると思います。ただ、現実として、大きな妨げになるのは事実ですので、落ち着かれるまで、ホールの外で対応して頂くようお願いします。
◆出入り
原則として、上演中の出入りは避けて頂きたいので、余裕を持って、会場にお越し下さい。止むを得ず、上演中に会場に入られた場合は、高齢の方や体調が良くない方以外は、後方でお待ち頂いて、暗転等のタイミングを見計らって、近くの席にお着き下さい。メガネ等の必要なものは、入場前に準備して頂いて、荷物の整理等は最小限にとどめて、音を立てたり、後ろの席の方の視界を、遮らないようにして下さい。
◆会話
おしゃべりはもちろんですが、緊急の場合を除いて、上演中は、一切の会話は禁止です。「あれ、鈴木さんとこの子?」とか「あの子上手ねぇ〜。」等、小声であってもお止め下さい。
3.最後に
お読みになって、「たかだか、中学生の公演で、重箱の隅をつつくようなことを」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、技術の善し悪しはともかく、どの学校の生徒も舞台を愛し、精一杯演じています。本当の意味で演劇部の活動を御理解頂き、応援して下さいますよう、お願いします。
1.会場に入ったら
会場での一般的な注意やマナーです。ご確認下さい。
◆開始時間
上演の開始時間は前後することがありますので、予定時間より早めにお越し下さい。
◆飲食
ホール内での飲食は禁止です。
◆喫煙
喫煙は喫煙所でお願いします。特に中学生の大会であることにご配慮頂き、他の場所での喫煙はお止め下さい。
◆拍手
開演時の拍手はご遠慮下さい。上演中に、演技に感動して自然に起こる拍手は制限しませんが、ストーリーの進行を妨げないように、充分ご注意下さい。
◆差し入れ
差し入れ等は、各学校のルールに従って行って下さい。ビン、カンやペットボトル禁止等、容器に制限のある場合もありますので、顧問にご確認下さい。
◆コート
厚手の服は音を吸ってしまいますので、ホール内に入ったら、コートやジャンパーの類は脱いで下さい。日本には、残念ながら、クロークが整備されていませんので、椅子の下に入れるのが、マナーとなっています。
2.上演中の注意
上演中のマナーの大原則は、「舞台と観客の集中を妨げない。」ということです。具体的に言うと、「余計な音や光を漏らさない。」ということに尽きます。よく、「フラッシュは、照明効果の妨げになるのでご遠慮下さい。」という説明がされることがあります。わかりやすいように、そう表現していますが、実際は、こちらの理由の方が重要です。
皆さん、舞台に影響を与える様なことは、しないように気を使って下さいますが、隣の席で、真剣に舞台を見ている方のことは、つい、忘れがちです。舞台に届かない音だから良いだろうとか、少しくらい構わないだろうと言う考え方は禁物です。
舞台上は夢の世界です。心ないフラッシュや携帯の音で現実に引き戻された観客は、なかなかもう一度、夢の中に入っていくことが出来ません。これは、皆さんに練習の成果を見て貰おうと頑張っている、生徒達の足を引っ張ることになります。
まして、この大会は、都大会に出場する代表を決めるコンクールも兼ねています。余計な音や光は、公平な審査の妨げにもなります。
ところが、フラッシュを焚かれる方や、ビデオのスイッチの電子音を立てられる方のほとんどが、保護者の方です。お子さんの晴れ舞台を、記録にとどめたい気持ちはよくわかりますが、ご協力下さいますようお願いします。
◆携帯
携帯電話やPHS等は、マナーモードではなく電源を切って下さい。バイブにしていても、近くの観客には音がハッキリ聞こえます。また、時計のアラームや時報等もオフにしておいて下さい。
◆カメラ
カメラのフラッシュやストロボは、大変集中を妨げますので、厳禁です。高感度のフィルム(ASA400〜800)を使用する等、工夫して下さい。また、一眼レフのシャッター音も非常に響きます。良い画を取りたいのは山々ですが、ご理解下さい。
◆ビデオ
ビデオ撮影は自由ですが、他のお客様の迷惑にならないように、なるべく最後方でお願いします。止む終えず、中央や前方の席で撮影する場合は、液晶画面は閉じて下さい。また、操作時の「ピピッ」という電子音は、メニューで消すことが出来ますので、事前にマニュアルに従って、設定をオフにしておいて下さい。
◆ポリ袋
コンビニ等のポリ袋は、少しの動作で非常に大きな音がします。なるべく、バッグ等を用意して頂いて、買ってきた昼食等の袋が、音を立てないようにお願いします。
◆パンフレット
上演中に配役等、気になることがあっても、パンフレット等をいじらないようにして下さい。紙のカサカサ言う音は、非常に耳障りです。
◆カバン
いわずもがなですが、現実には残念ながら、上演中にカバンをガサゴソ言わす方がいらっしゃいます。めがね等必要なものは、あらかじめ取り出しておいて下さい。
◆お子さん
小さなお子さんが、泣いたり、騒いだりするのは仕方のないことですし、各家庭のご事情で、会場に連れてこないと観劇が出来ない場合もあると思います。ただ、現実として、大きな妨げになるのは事実ですので、落ち着かれるまで、ホールの外で対応して頂くようお願いします。
◆出入り
原則として、上演中の出入りは避けて頂きたいので、余裕を持って、会場にお越し下さい。止むを得ず、上演中に会場に入られた場合は、高齢の方や体調が良くない方以外は、後方でお待ち頂いて、暗転等のタイミングを見計らって、近くの席にお着き下さい。メガネ等の必要なものは、入場前に準備して頂いて、荷物の整理等は最小限にとどめて、音を立てたり、後ろの席の方の視界を、遮らないようにして下さい。
◆会話
おしゃべりはもちろんですが、緊急の場合を除いて、上演中は、一切の会話は禁止です。「あれ、鈴木さんとこの子?」とか「あの子上手ねぇ〜。」等、小声であってもお止め下さい。
3.最後に
お読みになって、「たかだか、中学生の公演で、重箱の隅をつつくようなことを」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、技術の善し悪しはともかく、どの学校の生徒も舞台を愛し、精一杯演じています。本当の意味で演劇部の活動を御理解頂き、応援して下さいますよう、お願いします。
|
発表会当日の行動 |
演劇資料 |
上演許可申請の仕方 |
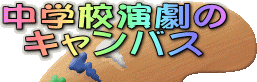
 パブリック・メニュー
パブリック・メニュー