鉄道・演劇・日常
主に、鉄道に関係する件の更新が多いかと思います。
更新頻度は、気まぐれなのでお楽しみに!
ふと思ったこと
daiman
2009年1月21日(水曜日) 16:53
僕が演劇部に入部したところから、今の演劇マニアに至り、けっこう多くの作品を見てきました。
学校でも、練習台本として、いくらか貰ったのもあり、様々な演出方法、舞台の使い方が頭をよくよぎらせたりします。
また、「パンフレット(リーフレット)集」の中の資料はここ3年の物だけですが、パンパンになっています。
では、中学時代〜今まで、どれだけ中学・高校演劇を見たり、台本を読んだのか?
部活で読んだ作品、個人的に買った台本集等を含め、合計作品総数
は、100作品以上。
最低100作品は絶対見ています。
「ずらずら書け!!!!」と言われると、正直面倒な作業なので、やりませんが、これは、間違いなく言い切れます。
台本を持っている数(本の中に数作品ある場合、それぞれを1作品とする。・例、1つの本の中に、タイトルが違う、7つの作品ある場合、7つ持っているとする。)
台本資料ファイルの中と、台本集の本の中の作品、全てごうけいすると、最低40作品は、あります。
行方不明のが見つかれば、50は超えるでしょう。
2回以上見た作品。桜井家の掟等、去年の都大会でもやった作品は、間違いなくここに入ります。
また、部活の時に、ビデオ、DVDで録画したものを見たのも含むと、合計は、最低10作品以上。
桜井家の掟、夏芙蓉、夢幻図書館、彼女によろしく、七人の部長、ハロマイ、ボクの自由帳、戦争を知らない子供たち、全校ワックス、おもいでかぞく。
最低でも、これらは2回は見ています。
最後に、ダイマンの、これまでで、印象に残っている作品BEST5!!!を紹介します。
これらは、僕が、今現在で、一番印象に残っている、作品です。
ちゃんと、理由もあります!!
まず、5位。→H19年の都大会より、中野ZEROホールで上演した、高島第二中の「修学旅行」
理由→枕投げのシーンは、客席から投げるという行動に、意表をつかれ、さらにクスミ君、アキラ先生等、笑いがよく取れていたから。また、それらが、今でも印象に残っているから。
次に、4位。→H18年、高校演劇の全国大会出場、島根県立三刀屋高校の「三月記〜サンゲツキ〜」
理由→演劇マニアとしての道の原点であるから。また、自分が「山本」のマネをよくしているから。
まだまだ行きます!!!3位→H19年の都大会より、中野ZEROホールでやった、三鷹四中の「桜井家の掟」
理由→これにより、「桜井家の掟」が大好きになり、現在の最高記録、合計6回見た(但し、学校は、全て違う)のを打ち出した。
上位になってきました!!な、2位→H18年の都大会より、中野ZEROホールでやった、三鷹四中の「七人の部長」
理由→台本を持っているため、内容を知っていたが、役者の反応・動作等、全国大会位レベルが高かったのが、今でも印象に残っているから。
キター!!!と思える、第1位!!!
H18年、代々木オリンピックセンターで上演した、神奈川県にある、鴨川中の「オアシス物語」
理由→今でも、障害のある役の役者の印象が残り、「小さな世界」を手話でやった、無音の世界が、不思議と心地よく、自分も世界に入り込んだから。また、オーナーのアナウンサー声等が、とても良かったから。
また、演劇好きの原点でもあるから。
以上です!!!
今思えば、本当に「オアシス物語」を超える作品にまだ出会っていないのです。
全国大会と、地区大会って本当にレベルが違います。
自慢しているような言い方で申し訳ないですが、演劇を見続けている、熟練者を、童心に返らせる位の感動・演技披露があれば、座をゆずるでしょう。
学校でも、練習台本として、いくらか貰ったのもあり、様々な演出方法、舞台の使い方が頭をよくよぎらせたりします。
また、「パンフレット(リーフレット)集」の中の資料はここ3年の物だけですが、パンパンになっています。
では、中学時代〜今まで、どれだけ中学・高校演劇を見たり、台本を読んだのか?
部活で読んだ作品、個人的に買った台本集等を含め、合計作品総数
は、100作品以上。
最低100作品は絶対見ています。
「ずらずら書け!!!!」と言われると、正直面倒な作業なので、やりませんが、これは、間違いなく言い切れます。
台本を持っている数(本の中に数作品ある場合、それぞれを1作品とする。・例、1つの本の中に、タイトルが違う、7つの作品ある場合、7つ持っているとする。)
台本資料ファイルの中と、台本集の本の中の作品、全てごうけいすると、最低40作品は、あります。
行方不明のが見つかれば、50は超えるでしょう。
2回以上見た作品。桜井家の掟等、去年の都大会でもやった作品は、間違いなくここに入ります。
また、部活の時に、ビデオ、DVDで録画したものを見たのも含むと、合計は、最低10作品以上。
桜井家の掟、夏芙蓉、夢幻図書館、彼女によろしく、七人の部長、ハロマイ、ボクの自由帳、戦争を知らない子供たち、全校ワックス、おもいでかぞく。
最低でも、これらは2回は見ています。
最後に、ダイマンの、これまでで、印象に残っている作品BEST5!!!を紹介します。
これらは、僕が、今現在で、一番印象に残っている、作品です。
ちゃんと、理由もあります!!
まず、5位。→H19年の都大会より、中野ZEROホールで上演した、高島第二中の「修学旅行」
理由→枕投げのシーンは、客席から投げるという行動に、意表をつかれ、さらにクスミ君、アキラ先生等、笑いがよく取れていたから。また、それらが、今でも印象に残っているから。
次に、4位。→H18年、高校演劇の全国大会出場、島根県立三刀屋高校の「三月記〜サンゲツキ〜」
理由→演劇マニアとしての道の原点であるから。また、自分が「山本」のマネをよくしているから。
まだまだ行きます!!!3位→H19年の都大会より、中野ZEROホールでやった、三鷹四中の「桜井家の掟」
理由→これにより、「桜井家の掟」が大好きになり、現在の最高記録、合計6回見た(但し、学校は、全て違う)のを打ち出した。
上位になってきました!!な、2位→H18年の都大会より、中野ZEROホールでやった、三鷹四中の「七人の部長」
理由→台本を持っているため、内容を知っていたが、役者の反応・動作等、全国大会位レベルが高かったのが、今でも印象に残っているから。
キター!!!と思える、第1位!!!
H18年、代々木オリンピックセンターで上演した、神奈川県にある、鴨川中の「オアシス物語」
理由→今でも、障害のある役の役者の印象が残り、「小さな世界」を手話でやった、無音の世界が、不思議と心地よく、自分も世界に入り込んだから。また、オーナーのアナウンサー声等が、とても良かったから。
また、演劇好きの原点でもあるから。
以上です!!!
今思えば、本当に「オアシス物語」を超える作品にまだ出会っていないのです。
全国大会と、地区大会って本当にレベルが違います。
自慢しているような言い方で申し訳ないですが、演劇を見続けている、熟練者を、童心に返らせる位の感動・演技披露があれば、座をゆずるでしょう。
リンク元 (935)
都大会感想〜ずらずらと字ばっかで読みにくい?〜
daiman
2009年1月14日(水曜日) 16:49
さて、都大会が終わり、3日経ちました。
僕も、疲れて、まだ食後すぐに寝て、11時に目が覚めるような生活が少々続いています。
やっぱり、3日連続で行くのは、体力使うけど、感動・笑いは、良い刺激になりました。
最初に、今大会での特徴を、さらっと書いておきます。
今回は、音楽を使うのが基本形態のようで、音楽・効果音を全く使わなかったのが、大田区立蓮沼中のみ。
それ以外の学校では、音楽・効果音を必ず使用していました。
2校ほど、役者が音に負けていたのが、残念でした。
役者は、都大会ですので、結構鍛え上げられていますね。
稲城5中は、稲城地区大会で見た時より、うん千倍よかったです。
まるで、アリが、恐竜になったかのようでした。
もちろん、板橋区大会でも、素晴らしく見せてくれた、「アニータ・ローベル」も、過去にさかのぼれば、数回都大会・全国大会に行っているだけあり、中学時代の僕だと、レベル的に絶対に勝てないような最高な劇を見せてくれました。
さて、さっそく下に、ずらずらずらと感想・評価を書いていこうと思います。
レベルについてですが、一番低いレベルは、「練習以下」です。(地区大会でも付ける事はあまりないくらい)また、最高レベルは「全国大会並」と表記します。
詳しく下から順に書いていくと↓になります。
練習以下→練習並→地区大会並(区大会並)→都大会並→関東大会並→全国大会並。
また、〜が入っている場合は、その中間くらいと思ってください。
さて、今度こそ本題に入ります。
世田谷区緑ヶ丘中
「天空と未来の夕焼け」(創作)
声は、聞きづらいが、声量は、良かった。
アドリブも多く、逆に負けていた。
裏方は、イマイチであったが、役者はなかなか良かった。
動きが少ない代わりに、伝える力、中村カイトのバカっぽさが非常に良かった。
台本の質は、少し創作が入っている感じ。
学生の雰囲気がよくでていた。
だが、被り、後ろ向きが多く、声が聞こえない時があった。
音は、大きすぎる時もあったため、レベルは、区大会レベル。
東村山第六中
「アイズ(中学生版)」役者は、普通の都大会レベル。
照明の使い方も良かった。
また、家族の中の出来事は、上手に表現できていた。
だが、後ろの、主人公の頭の中の住人は、普通だった。
ストップモーションも良く、レベルは、都大会レベル。
伝えるように語りかけていたので、全体的には良かった。
東綾瀬中
「つばめ〜ワイルド作『幸福な王子』より〜」
正直地区大会レベルだった。最後の最後で少し良くない面があり、残念だった。
役者は、関東(全国?)に行った事は、まだわかるレベルだったが、正直普通レベルだった。
良い点は、語りかけるような口調であった事だった。
良くない点は、音響の使いすぎ&暗転がだんだん長くなっている事だった。
旭丘中
「桜井家の掟」
今回を含み6回見た中で、3番目に良かった。
光一・父は、もう少し工夫した方が良いと思った。
真紀は今まで見た中で、一番良かった。
また、窓が横にあるのに、光一・母の窓のやつができるのは驚いた。
また、新工夫として、お母さんとのボコボコシーン(父・不良)が、目の前で見れる工夫と、光一・母の「返事!!!」のセリフが良かった。
地元ネタを使用していて、良かった。
「池袋」で事件、「練馬方面へ逃走」、「板橋第一小学校6年3組」、「ブクロキッズ」等
笑いも結構取れていた。
レベルは、都大会並。
駒込中
「王子がくれた物語」
ダンスを見せるばっかだったので、劇という感じがあまりしなかった。
レベルは、区大会レベル。
ただ、裏方のドアの工夫(ブラックライト等)は、とても良かった。
役者は、都大会の中では比較的低いレベルであった。
「アニータ・ローベル」
赤塚一中
役者は、とても上手で、照明の使い方もバッチシだった。
音は沢山使っているように思うが、意外と適度な量で、丁度良かった。
戦争物だったが、「血」を示す赤い照明も、良く、とても良かった。
雰囲気や、間の取り方もけっこう良かった。
レベルは、都大会レベル。
「グッドバイ・マイ・・・・・」
田端中
役者は、なかなか普通であったが、動きは、比較的多かった。
おそらく、その日の見た中で一番多いだろう。
照明等裏方は、まあまあの出来であった。
レベルは、地区大会〜都大会レベル。
「花柄マリー」
南大谷中
越智優ワールドがいつも通りの雰囲気で始まり、「越智優さんの作品だっ!」と思いました。
役者は、まあまあ普通であったが、地区大会レベルな感じだった。
越智さんらしく、最初に笑い、後に感動の感じだったので、まだ良い方だった。
照明は、めちゃめちゃ普通だった。
だが、コケた時のアドリブが偶然の場合、対応がバッチシであった。
もしも、演技だった場合、「偶然のように見せかけている」演技となるため、演技が上手と考えられる。
↑走り回っている時に、コケそうになり「大丈夫?」と聞き、「大丈夫じゃない」と言ったアドリブのシーン。
全体レベルは、地区大会〜都大会並。
1日目の平均レベルは、地区大会〜都大会並。
1日目終了!
2日目
夢幻図書館へようこそ」
葛西第三中
去年の都大会作品。
先にレベルを発表します。
都大会〜関東大会レベル。
理由としては以下。
・役者が、完璧成りきっていて、去年の目黒を越えたレベルだったから。
・夢幻図書館の開館時、去年のような「チカチカ」したような照明が緩和され、さらに扉が左右から出てくる感じが良かった所。
・ダサイ、オサムが前回より良かった所
・未来の先生が、ダサイ、オサムと太宰治の価値観を大きく差をつけている所。(太宰治ファン?)
「(惚れてるように)あの太宰先生と、(怒った感じに)こんなダサイと同じにしないでっ!」
・過去のあの大女優の行動等。
悪い点は、笑いが少ない所。
また、夢幻図書館での、大女優や、未来の先生、ダサイ・オサムの登場する時の工夫が少し違いました。
原作は、後ろの扉が開いて、そこから来ます。
今回は、扉のパーツが左右から動いて来るので、その扉の後ろ(扉は、後ろからワームが支えて、動かしている)から現れるのです!
つまり、ワームと一緒に隠れているわけです。
その登場の仕方は、最初に予測できましたが、素晴らしくできていました。
もう一点、素晴らしい工夫が施されていたのは、マイクについてです。
最初の図書館開館時、マイクで夢幻さんが発言後、わざとマイクをトアノさんの机において、パソコンを打つ時の「カチャカチャ」という音を、トアノさんが叩いて表現していました。
机を叩く(爪で音をたてる?)のを大きく、さらに同時に表現する事において、最高かつ素晴らしい工夫でした。
しかし、デメリットとして、一部のセリフがいつも以上に大きく聞こえるため、聞きづらい時もありました。
ですが、ワームで笑いをとれない所が残念だった。
また、抵抗する所をできない感じがあり、残念だった。
トアノさんは、アナウンサー声ではないが、似合っていた。
夢幻さんは、なかなかバカっぽかったです。
「おもいでかぞく」
東山中
去年の都大会作品
正直、明日の稲城にも負けそうな位のレベル。
地区大会レベル。
まだ、内容がわかるのであるが、棒読み、棒人間(つったったまま話す)が多く、去年が良かった。
お父さんが特にひどかった。
なぜなら、尻向け・棒読み・棒人間で最悪だったから。
その他の役者は、少し悪い位のレベル。
有希は、子供っぽくなく、少し似合って無かった。
これは、昨日の全部よりも下の実力であった。
「夏休み」
日野学園(品川)
〜斎藤さん作品〜
大場憲一(バケ)の話。
都大会レベルの作品。個人的には赤一と同等のレベルを持つ。
最初のバケが話す時の口調(ちなみに演じている人は、外国人の小6)が、本当によく出来ていて、引き込まれた。
声は、アンパンマンに似ている感じである。
役者は、上手く、役者だけなら、都大会以上のレベルである。
照明も良くできていて、全体的にまとまっていた。
暗転時は、森の妖精がセットする等飽きない工夫があった。
言い方、口調等、役者は、完璧だったが、全国大会のように印象を深く与える事は、あまり無かった。
「『ああ野麦峠』から繭のうた」
足立第十一中
昔の后女を鮮明に描いた劇で、感動を与えた。
僕も、うるうると来た位、泣かせる劇だった。
役者は、そこそこ良く、レベルは、都大会レベル。
吹雪の中の表現等が良かった。
役者を詳しく評価すると、言い方は、一部棒読みがあり残念だったが、動作・アドリブ・言葉の表現はとても良く出来ていた。
また、始まる時、三味線を生で引いて、語る、驚きもあった。
三味線は、何回か出てきて、おばあさん(現在)の話の時は、引いていた。
糸をつむぐシーンは、自分の手で、上の糸回しを回しそれに合わせて、下で手を動かしていました。
裏方もよく出来ていた。
「夏が終わったら」
府中市立浅間中
〜創作台本〜
役者は、亀尾さん風、脚本は、越智さん風でした。
役者は、なかなか良く、伊豆諸島の島の少女らしい元気さでした。
落ちは、「すっぱいブドウ」のような、最後に自分達の思いを伝える感じでした。
意外な小役では、魚隊長と魚兵士の2匹(隊長にアルミ缶があたり、死にそうだから、隊長が隊長の座を譲る→生き返る=隊長の座は、そのまま?→若い人が使う言葉『○○だしぃ〜、カラオケってるしぃ〜』を兵士が使う(『ぼけちゃってるしぃ〜』のような言葉を含む)隊長も使い、若さを主張等。はける時は「ひからびそうだから。Bye」)や、かっぱがありました。
かっぱは、
少女「あなたは誰?」
かっぱ「かっぱ?(疑問型)」
中略
少女「あっでもお皿割れてるから、かっぱじゃないね」
かっぱ「んじゃあかっぱやめる。パッカになる。」
と、かっぱが脱力系な感じで言う等、面白かったです。
暗転はなく、出だしは、上手→真ん中→下手の順に3人の少女の理由を当てていたので、照明の工夫は、これだけです。
レベルは、地区大会レベル
「夏扶養」
亀有中
越智優作品。
これは、後輩に見せた方が間違いなく良い作品に仕上がっていました。
舞子ちゃんが上手く、実力がありすぎる役者でした。
その他の役者は、言葉関係全部、感情、行動、立場、キャラクターの思考までもが本物のように感じました。
ちーちゃんと舞子ちゃんの過去のシーン(ハムスターの「ぐり・ぐら・ぐる」の話と、長机を運んでいる時に見た、夏扶養の花の話)の時は、ピンスポで当てて、仲の良さ等人情を表現、サエちゃんとタマイの「プリッツ&ポッキー&醤油味せんべい」の件は、↓の通り。
プリッツ&ポッキー
サエ「プリッツ全部折ってやった!」
(プリッツにひざげりをする)
間
サエ「袋ごと!」
せんべい
サエ「せんべい全部割ってやった」
(せんべいを下にたたきつけて、足で踏みまくる)
間
略
という感じで、面白かったです。
ただ、タマイは、元気すぎるタマイで、おとなしいイメージをがらっと変えました。
「タマイって、のろまじゃない?」のセリフが無かったので、様々な面できちんとそろっていました。
最後は、台本では、舞子だけが「みんな卒業したっ!」と言いますが、今回は、舞子が行動で、無言時を表現もし、最後は、勢揃いしました。
レベルは、都大会〜関東大会。
印象に深く残り、役者、照明、音、全て良くできていました。
最初と最後は、一人でもだいぶ良い劇でした
「彼女によろしく」
蓮沼中
去年のが最高でした。
去年は、全てが笑えるシーンだったのに、今年は、去年大笑いのシーンの所が通常の笑い。
その他は、「シーン」としていました。
役者も基礎は、できていても、感情、言い方、雰囲気が欠けていた感じです。
珍しかったのは、暗転が、お客が必ず舞台のセットが見える位明るい状態で行われた事。
2回目の暗転では、それにより、電子部がロッカーに隠れる所を見て、笑いが起きました。
また、音を全く使わない劇で、最初は、良いと思いましたが、最後の最後が、役者の力不足より、音が入っていたら、最高な終わりにできると思いました。
最後は雰囲気で「開けた?感じ→開いた!行こう!とうなずく(僕は、なぜうなずいたかわからなかった)→去る」という感じでした。
レベルは、地区大会〜練習並
※練習並といっても、「本番1週間前位の時」という感じです。
簡単にまとめると、役者は、イマイチ、裏方は、ミスあり?という感じの劇でした。
「吹雪よ我が挽歌となれ」
墨田区立寺島中
最初、吹雪の音(落石っぽくも思えた)があり、登山者2人が凍えるシーンから始まります。
そして、山小屋らしき所に変わり、先ほどの登山者の妻と、登山者仲間が話をします。
話は、おおまかに言うとこんな感じです。
「命」について、表現する話ですが、審査員がそういう話をしている所から、「成程」と思いました。
正直、役者は、尻を向けまくり、単調、棒読み、動きほぼ無し、言葉関係不十分でした。
まだ、雰囲気は、ものすごく出ていて、いや、最初だけ出ていて、後は、あまり出ていない感じでした。
裏方では、照明が真ん中のピンスポと、右側のピンスポだけで、済ませられていたので、意外と簡単な作りでした。
この劇は「男2女1」ですが、男3でも間違いなくできますが、質は正直良くないです。
レベルは、練習並。
以上で2日目終了です。
3日目
「クロワッサン」
深川第三中
創作作品。
創作の割には、台本の質がこの上無いくらい上手だった。
最近の「偽装問題」を取り入れていて、閉店におちいる所から、バッドエンドかと思ったが、最後は、チェーン店の前に店長がやっていた、小さなパン屋を再開というハッピーエンドに納めたのが、意外で、感動を増せた。
必ず来年、どこかでやる台本だろう。
役者や、裏方については、被り、雰囲気が無い尻向けがあったが、役者は、都大会レベル、裏方は、多少、人が写らない所があり、少し悪かった。
ただ、言葉の雰囲気や、言い方等は、素晴らしい物だった。
そのため、鼻をこする人が多く、僕も少し「うるっ」っときた。
人情を感じるのには、最適だろう。
ただ、始めから終わりまで、曲を使っていた。
だが、それがあるからこそ、感動を与える劇になった。
声量は、一部音楽に負けていた。
ちょっとの改善で間違いなく全国は行けるレベルだろう。
最後の所は、薄い白幕を透かして、後ろを出していたので、舞台の使い方がポイントな劇。
総合でのレベルは、都大会〜関東大会並。
「KYO−GeN」
松ノ木中
創作作品。
単に狂言をやっているかと思ったら、2本目の狂言の芝居時に、「こう・こう・こけこっこう」と「びょう・びょう・びょう」と言いながら、○○こうと「エド・はるみ」みたいに連発していた。
始まった中学校
宿題忘れて再登校
だけど天気は、悪天候
家に着いたら日光
永福町から乗る急行(京王井の頭線)
彼女を涙で見送る成田空港
等、ここは、大笑いしました。
どうしても言い方が、単調になりやすいのが、古典文学の特徴ですが、あまりに単調すぎて、前述の笑い所以外つまらない雰囲気がありました。
役者も、動き(2番目の酒の話では、手を縛られている人がいたので、その人は、一部の動きを除く)が少なく、もう少しオーバーにやっても良い感じがありました。
レベルは、都大会位で良いでしょう。
「タヒムマシン」
稲城第五中
35分間の劇でした。
何か、ありが恐竜になったような進化をとげました。
言い換えるなら、山手線が「新幹線」になるという位です。
役者は、声量以外都大会〜関東大会レベルになり、素晴らしくできていました。
あきら(3年の馬鹿な先輩)役は、「おでこビーム」、「旗がハタハタしてる」、「この長椅子、ながいっすね。」というネタをやったり、「俺の好きな言葉は、ハーゲンダッツだぁ〜!」と修学旅行のクスミ君みたいに、なっていました。
笑いは、必ず起こせていました。
裏方は、一部ミスがあったため、地区大会レベルでしたが、役者の雰囲気等(声量は、女子がダメなので除く)は、良かったです。
動作は、無くても伝わる劇ですが、少し少なすぎかと思う位でした。
レベルは、都大会並。
少し改善があれば関東大会と言っても良いでしょう。
「彫刻の森へ」
調布第六中
創作作品
台本の質は、クロワッサン並に良くできていた。
だが、音を劇の半分位使っていた。おおまかな内容としては、19時30のロマンスカーで箱根湯本へ。
バスに乗り換えて彫刻の森へ行く。
理由は、親が愛していない、友達関係がうまく行ってないから。
また、それらが長く続いたから。
だが、彫刻の森の彫刻を見て、「自分は、愛されている」事を学ぶという内容です。
ちなみに、彫刻は、自分史になっていて、生まれた頃〜小学校時代の出来事〜未来の自分(彫刻は無い)となっている。
役者は、活舌の問題以外は、特に指摘はない感じである。
言葉の伝え方等も、良くできていた。
「暗転」と言える暗転は、無く、お客を上手に引かせて、その間にセットするタイプだった。
裏方は、ミスがあったが、うまかった。
レベルは、都大会並。
「星がまたたいた夜」
荒川区立第五中
戦争関係物。
現在のごく普通の生活に、主人公の少年のおじさんに当たる人(戦死した)達が友達を連れてきて、戦争と現在の違い・命の大切さを伝える劇だった。
ハーモニカを引くシーンがあるのだが、そこは、「ふるさと」の曲を引く。
だが、半音ずれていたり、吹けてなかったりでダメだった。
役者も動きが少なかった。
だが、動きが少ない方が逆に良く、雰囲気等の観点は、完璧で、レベルは赤一くらいあった。
照明は、一部当たっていなくて、工夫が必要と思った。
ただ、周りの4割の人は、少しでも涙を流していた。
レベルは、今回は、都大会並。
ハーモニカが良かったならば、関東大会並。
また、この劇より、昨日1位と思っていた夢幻図書館は、桜井家と同等、またはそれ以下と思えた。
「全校ワックス」
東京大学教育学部付属中等教育学校
高校演劇。
意外な形が目だった劇でした。
それは↓
1、先生・教育実習生がいて、時々見回りにくる。
先生は、怖い性格のため、生徒に話しかけられる事が無く、嫉妬を見せる(笑いが起きる)
教育実習生は、バケツをかぶる!(生徒から「かぶって!」とはやしたてられたため。→笑いが起きる)
2、相川が男!(イメージは、同じ・陸上部)
3、江川さんが、白人の子(バケツシーン等は、非常にうまかった)
照明は、異常なし。
役者は、がらっと変わる雰囲気も、笑いの雰囲気も存分に出せていた。
元の高校演劇並に良かった。
動きも、声量も、アドリブも全て良かった。
また、各動き(最後のシーンを除く)で、必ず笑いをとっていた。
だが、残念だったのは、最後の
「せーの、(全員で)え。」
でも笑いを起こしてしまったこと。
そこは、完璧に雰囲気が出せていなかった証拠と思われる。
告白ごっこは、グループ歌手の立ち位置等、台本に無い設定があった。
今回は、元の設定+台本に無い設定=素晴らしい劇
となり、笑いを多すぎにした物になった。
レベルは、関東大会並。
今でも、教育実習生のバケツが印象に残っています。
ちなみに、バケツをかぶった後の踊りは、音楽付きで、後に出てくる島の周りを踊り、走っていました。
江川が最初にかぶった時もそうでした。
「陪審員・映画『12人の怒れる男』より」
南大沢中
創作作品。
この劇の役者の中で、怒りんぼというか、感情的な人がいるのですが、その人が、本当に不良っぽいというか、本当に上手で、これまでに見た作品の中で一番良かったです。
役者は、皆最低でも区大会レベルで、上手かったです。
雰囲気のだしかた、言葉、感情、全て良かったです。また、本気で机を叩いている等(手が本当に痛くなりそうな位)、迫力もありました。
裏方は、音の音量も、照明もバッチシでした。
1日目とは大違いです!
舞台は、机、ソファ、帽子掛と簡単な作りでした。
ただ、残念な事に、机を真横に置いた(並べた)ために、後ろ向き・被りが発生してしまい、見えない人が必ずいました。
全体的には都大会〜関東大会レベル。
被りがなければ、全国も行けそうです。
「メイドイン・ポイズン」
日野第四中
創作作品。
あまりよくない作品でした。
台本の質は、良いとしても、役者がダメでした。
動きが少なく、声量は良いが、雰囲気が出せたり出せなかったりしていて、ダメでした。
久しぶりに、アニメ声を聞きました!
お嬢様は、アニメ声で、雰囲気は出ていました。
裏方は、この都大会全体で一番ダメな使い方で、顔も見せてくれず、黒い影が行動する感じになりました。
また、暗転中に明かりが付きそうになったりしていて、ダメダメをはっきり証明していました。
レベルは、練習〜地区大会並です。
はぁはぁ。
こっこれで全部です。
長時間お読み頂きありがとうございました。
是非、読んだ感想等をコメントしてくれると幸いです。
リンク元 (7903)
賀正
daiman
2009年1月05日(月曜日) 10:48
100KB以下の工夫の試しに、少々カメラでは画質が悪いのを添付してみました。
添付した後に、内容をかいているので、どれぐらいの画質だと良いのか確認完了です。
今回は、お正月休みに鉄道好きな「いとこ」と共に、祖母の家の近くの撮影ポイントに行ってきました。
ここは、左の山をバックにするのが基本ですが、そっちは、写真の条件に合わないので、諦めます。
これでも、後ろの山(浅間山)は、幼いころからの好きな山で、この日のように晴れていると、とても美しく見えます。
そんななかを走るキハ110です。
さて、写真の前置きが長くなりましたが、本題に入ろうと思います。
まず最初に、前回指摘があった、「大木君」について。
大木君(たいぼくくん)とは、状況によりますが「腕を組んで、口以外全く動かない人」です。
ちなみに、女性だと「大木さん」(たいぼくさん)です。
地区大会レベルだと、ここで、大きな差がつくことがあります。
都大会では、まず見かけないケースでもあります。
目黒第八中がやった、「夢幻図書館へようこそ」は、みんな知っていると思います。
それを例にあげて説明しましょう。1週間後に行われる都大会でも、やりますし。
結構中盤まで省略します。
なんだかんだで、明治か大正時代の作家で、着物を着ている「ダサイ・オサム」が現れます。
そして↓のように表現したとします。
「現れた→無言で動いて、自分の位置についた→腕を組んだまま立ちっぱで、話す。」
昔の男性のイメージは「一家の主で、食料を作っているから、飯の量は、家族の中で一番多いんだ!!!」っていうような、いばっているイメージがあります。(社会の教科書にも、そんな感じの事がのっているはず。)
そうでなくても、武士の時代の名残で腕くみをする人が多いと、考えられます。
そこから、腕くみをするのはまだ良いのですが、無言で動いて、そのまましゃべる。
なんか、役者の立場等がつかみずらいと思いませんか?
このような時は、↓が良いと思います。
「現れた→セリフ(アドリブも可)を言いながら、自分の場所に動く→立っているならば、最低でも、一部を除くセリフの時は、腕組み以外の行動を取る」
という感じです。
これで、つかみにくい人に、もうひとつ例をあげます。
体育の先生って、人にもよりますが、腕を組んでいる人って多いと思いませんか?
注意するときって、腕を組んだまま「うぉい!!!ダイマン!!!そこはトスだろ!!!」ってまあ、言う人もいるかもしれませんが、根気よく指差しをする人が多いと思います。
サッカーの場合も、「行け!!行け!!ダイマン!!ゴールが、がら空きの今がチャンスだっ!!!」って、腕組みの状態で動かないで言うと、迫力が無いのを感じませんか?
少しでも、体を傾ける等したら、まだ体育の先生っぽいと思います。
そんな感じのケースです。
僕の実際の経験では、はじっこで、つっ立ったまま、大木君をやった、背の高い男子がいて、その時、生徒の方から「大きい木みたい!!」→「大木みたい」→「大木君だっ!!」
というようなひょんなことからできたのです。
様々な地区大会を見ていると、意外にもそんな人が多く、上手な人は、絶対にしないのです。
していたとしても、状況に合っている時のみなんです。
雰囲気が出ていれば、自然と動作からも劇を読み取ることができます。
「耳の聞こえない人にも、劇の趣旨を伝える」ようになっている人は、僕でも高評価を下します。
実際、初恋(片思いだが)のTさんは、そんなのも余裕でこなし、セリフをその場に合った感情で数回練習したら言えるような、「演劇の魔女」のような存在でした。
結論として、大木君(大木さん)の定義として「腕を組んで、口以外全く動かない人」の事。
・・・・
ただし、お客さんから見て、状況があっている時は、しても良い。
という感じです。
さまざまな劇をみれば、自然に意味がわかってくると思います。
最後に、正月に行った路線紹介。
今回は、「東京→高崎→佐久平→小淵沢→甲府→富士→三島→東京
」と行きました。
途中、深谷・高崎・小淵沢・甲府・富士・三島で途中下車しました。(祖母の家の最寄り駅を除く)
深谷は、東京駅みたいに、赤レンガでできていて、本当に「偽東京駅」でした。
町並みは、田舎っぽい感じでしたが、駅の出口から徒歩10秒の位置に神社がありました。
赤い橋も目立ち、途中下車してみないと、わからない風景を見てきました。
高崎は、駅前をぶらり。
ダルマの絵がなんとなく勇ましい感じがありました。
EF55弁当は、正直買いたかったのですが、金欠。
小淵沢も駅前散策。
晴れていたので、野辺山付近の八ヶ岳も最高でしたが、小淵沢駅付近から見る富士山、八ヶ岳連峰も最高でした。
甲府は、スイカが使える駅なので、チャージ・履歴印字をやりました。
身延線に乗り、富士の山麓の景色を楽しみ、富士山もきれいに見えて、いつの間にか静岡県富士宮市。
JR東海の特急チャイムも聞けて満足しながら、富士駅で途中下車。
お正月休みの影響で、商店街は荒廃したかのようにがらがら。
人がいたら、大賑わいな感じでした。
そして、普通列車に揺られ三島へ。
過去のブログにもあるように、また三嶋大社に行きました。
お守りも買って、お祈りをしてきました。
三嶋大社の巫女さんは優しく「お参り、お疲れ様です」と、言ってくれて、自分のその時の感情は、秋葉系な言葉で言うと「萌ー」な感じでした。
なんか、こう、男心をくすぐられるような言い方で、まさに、天使のような存在と思えました。
帰りは、生まれて初めての東海道新幹線で、東京へ。
座って鉄がしたいがために、新横浜まで「こだま」。
新横浜で「のぞみ」(N700)に乗り帰りました。
西日本・東海の両社の車両に乗れて、良かったです。
TOKIOの「アンビシャスジャパン」も聞け、山口百恵の「いい日旅立ち」も聞けて、最高な日をすごしました。
リンク元 (88)
PopnupBlog V3 Denali created by Bluemoon inc.


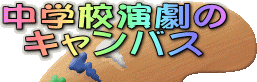
 パブリック・メニュー
パブリック・メニュー